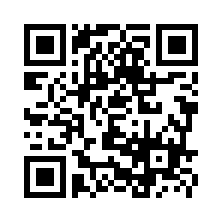2025.01.24
【家族信託】家族信託の活用事例 ~認知症対策から事業承継まで~
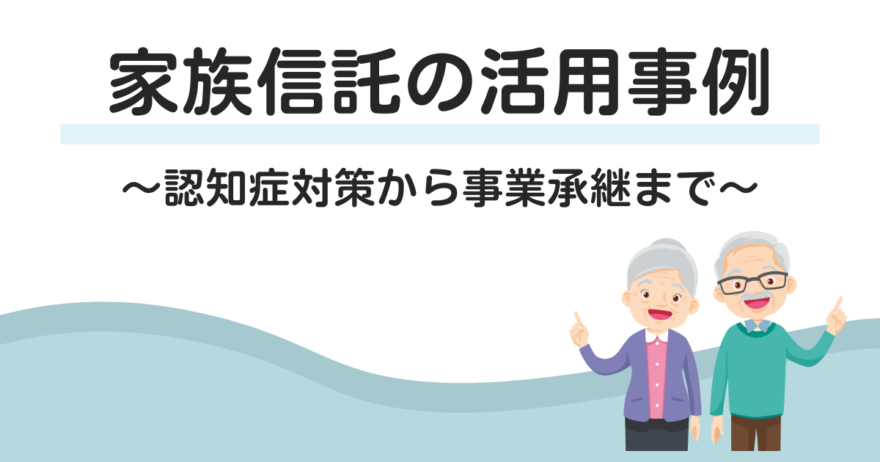
認知症による資産凍結を防ぐ家族信託
認知症発症後の資産管理の課題
認知症が進行すると、預金口座が凍結され、不動産取引も困難になることがあります。家族信託を活用することで、これらのリスクを回避し、安定した資産管理が可能になります。
認知症になると、ご自身の意思で財産を管理・処分することが難しくなります。銀行口座からの払い戻しや不動産の売却などができなくなり、日常生活に支障をきたす可能性もあります。
このような状況を避けるために、認知症になる前の対策が重要です。家族信託は、その有効な手段の一つとして注目されています。
家族信託の設計と具体的な対策
信託契約によって、財産の管理・運用を家族に委ねることができます。受託者となる家族が、信託目的に従って、資産を適切に管理します。
家族信託では、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を管理・運用する人)、受益者(財産から利益を得る人)を決め、信託契約を締結します。
認知症対策として活用する場合は、親が委託者兼受益者となり、子が受託者になるケースが多いです。信託契約の内容は、家族の状況や希望に合わせて自由に設計できます。
認知症対策としての家族信託のメリット
資産凍結リスクの回避、柔軟な財産管理の継続、成年後見制度利用の回避など、多くのメリットがあります。
家族信託を利用することで、認知症発症後も受託者が財産を管理・処分できるため、資産が凍結されるリスクを回避できます。また、信託契約の内容によっては、認知症の進行度合いに合わせて柔軟な財産管理を行うことも可能です。
成年後見制度は、家庭裁判所の監督を受けるため、財産管理の自由度が低いという側面があります。家族信託は、成年後見制度と比較してより柔軟に財産を管理できる点が大きなメリットです。
不動産トラブル回避のための家族信託
共有不動産に関する問題点
共有名義の不動産は、売却や管理において共有者全員の同意が必要となり、意見の対立が生じやすいです。家族信託を活用すれば、こうしたトラブルを未然に防げます。
例えば、兄弟で共有している不動産を売却したい場合、兄弟全員の同意が必要です。意見が対立した場合、売却がスムーズに進まない可能性があります。また、共有者の中に認知症を発症した方がいると、さらに手続きが複雑になります。
家族信託は、このような共有不動産特有のトラブルを回避するための有効な手段となります。
信託による不動産管理の一元化
家族信託を活用すれば、受託者に不動産の管理を委ねることができ、単独で不動産を管理・活用することが可能となります。不動産の共有トラブルを回避できます。
家族信託では、不動産の所有権を受託者に移転します。これにより、受託者は単独で不動産の管理・運用、売却などの処分を行うことができます。共有者全員の同意を得る必要がないため、スムーズな不動産管理が可能です。
不動産管理の手間を軽減したい場合や、将来の共有トラブルを回避したい場合に、家族信託は有効な選択肢となります。
不動産信託による円滑な資産承継
家族信託を活用することで、不動産の相続や贈与をスムーズに行うことができます。遺産分割協議の複雑化や不動産の共有問題も解決できます。
相続が発生した場合、遺産分割協議によって不動産の分割方法を決定する必要があります。共有状態の不動産は、分割が難しく、遺産分割協議が長期化する要因になります。また、共有状態のまま相続が発生した場合、さらに権利関係が複雑になる可能性があります。
家族信託を活用することで、不動産を承継する人を指定したり、相続後の管理方法をあらかじめ決めておくことができるため、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。
想いを実現する家族信託:資産承継の自由度を高める
資産承継における自由な設計
遺言では実現が難しい細かな財産配分や、特定の用途に限定した財産の使用を、家族信託を活用することで可能になります。ご自身の想いを形にすることができます。
遺言書では、誰にどの財産を相続させるかを指定できますが、その後の財産の使い方や管理方法まで指定することはできません。例えば、特定の子供に財産を相続させたいが、その子供が浪費癖があるため、財産管理を任せられないといった場合、遺言書だけでは対応が難しいです。
家族信託では、財産の管理・運用方法や、受益者の権利などを細かく定めることができるため、ご自身の想いをより柔軟に実現することができます。
二次相続以降も考慮した信託設計
受益者の指定や変更を柔軟に行うことができ、二次相続以降の財産の承継先まで含めて設計することが可能です。
遺言書では、一次相続(親から子への相続)までしか指定できません。二次相続(子から孫への相続)以降の財産承継については、遺言書で指定することはできません。そのため、遺産分割協議が複数回発生したり、相続のたびに相続税が発生したりする可能性があります。
家族信託では、受益者を複数世代にわたって指定することができ、二次相続以降の財産承継まで見据えた設計が可能です。これにより、相続手続きの簡略化や相続税の節税効果が期待できます。
資産承継におけるトラブル防止
家族信託は、遺言書よりも柔軟で、より具体的な資産承継が可能です。そのため、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、家族間の紛争を回避する効果が期待できます。
遺言書の内容によっては、相続人同士で解釈の違いが生じたり、遺留分を侵害しているとして紛争につながる可能性があります。遺産分割協議がまとまらず、裁判所に持ち込まれるケースも少なくありません。
家族信託は、契約内容を明確化しやすく、相続人間の認識のずれを少なくすることができます。そのため、遺産分割協議のトラブルを未然に防ぎ、家族関係を良好に保つことができます。
事業承継に役立つ家族信託
事業承継における株式の扱い
非上場株式の承継は、後継者への事業承継において非常に重要です。家族信託を活用すれば、株式を後継者にスムーズに承継させ、事業の継続を円滑に進めることができます。
非上場株式は、上場株式に比べて換金性が低く、相続が発生した場合に分割が難しいという特徴があります。後継者以外の相続人が株式を相続した場合、経営権が分散し、事業承継がスムーズに進まない可能性があります。
家族信託では、後継者を受益者として指定することで、株式を後継者にスムーズに承継させることができます。これにより、後継者は経営権を確保し、事業を円滑に継続することができます。
経営権の移行と事業承継
経営権を後継者にスムーズに移行させることで、事業の継続を円滑に進めることができます。家族信託は、経営権の移転と、後継者の育成を同時に行うことができます。
事業承継では、単に株式を後継者に承継するだけでなく、経営権をスムーズに移行させる必要があります。経営権の移行がスムーズに進まないと、後継者が十分に力を発揮できず、事業が停滞する可能性があります。
家族信託では、信託契約の内容によって、後継者に経営権を段階的に移行させることが可能です。また、信託期間中に後継者の育成を進めることで、スムーズな経営権の移行と事業承継を実現することができます。
事業承継における家族信託の活用
後継者が複数いる場合でも、家族信託を活用することで事業承継を円滑に進めることが可能です。後継者間の紛争を未然に防ぎ、事業承継を円滑に進めることができます。
後継者が複数いる場合、誰にどの事業を承継させるか、経営権をどのように配分するかなど、検討すべき課題が多くあります。後継者間で意見が対立し、事業承継がスムーズに進まないケースも少なくありません。
家族信託では、後継者ごとに受益権の内容を変えることができ、柔軟な事業承継が可能です。また、信託契約の内容を明確化することで、後継者間の紛争を未然に防ぎ、事業承継を円滑に進めることができます。
家族信託の多様な活用法
家族信託は、認知症対策、不動産管理、資産承継、事業承継など、多岐にわたるニーズに応えることができます。家族信託の活用を検討することで、より柔軟で、安心な財産管理、承継が実現できるでしょう。
家族信託は、財産の管理・運用を家族に委ねることで、様々なリスクを回避し、ご自身の想いを実現するための有効な手段です。信託契約の内容は、家族の状況や希望に合わせて自由に設計できるため、より柔軟な財産管理・承継が可能です。
個別面談の申し込みは
家族信託は、専門的な知識を必要とするため、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談しながら、慎重に進めることが重要です。
個別相談をご希望の方はこちらからお申込みください!
<当事務所LINE公式アカウントQRコード>

↓こちらのURLをクリックすると、当事務所のクチコミが投稿できます!
匿名やコメントなしで★評価だけでも構いません。ぜひ感想をお寄せください!
https://g.page/r/CVHCkNTn6fJiEAE/review
<登記・債務整理・家族信託・相続のクチコミQRコード>
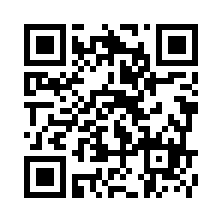
↓こちらのURLをクリックすると、当事務所のクチコミが投稿できます!
匿名やコメントなしで★評価だけでも構いません。ぜひ感想をお寄せください!
https://g.page/visa-fukuoka/review
<許認可申請・ビザ申請・補助金申請のクチコミQRコード>